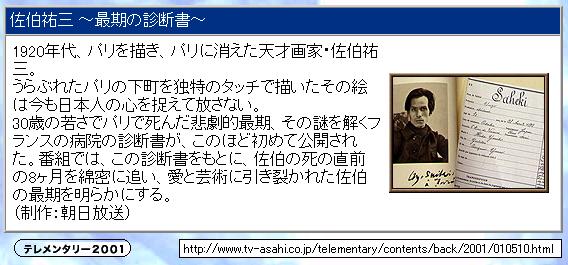| し け ん ど く は く |
|
し け ん ど く は く |
佐 伯 祐 三 編
2006/08/15
「私見独白」 特 別 版 平成13年5月10日(映像:「テレメンタリー 2001(*)」) * 「テレメンタリー2001」はテレビ朝日系列の全国 24社が 共同で制作するドキュメンタリー です。 以下は日本病跡学会の記録とヴィル・エヴラール病院の診断書である |
||
(映像:佐伯祐三ライフマスク→佐伯作品「郵便配達夫」など作品数種) ナレーター 保坂和拓(以下、「ナ」と記す。)/パリを描き、パリに消えた洋画家・佐伯祐三(さえき ゆうぞう)。果てしない芸術の高みを目指し、全力で走り続けた30年の生涯。亡くなる5ヶ月前までパリで描き続けた作品は300点を越す。命の炎を燃やし続け、新たな飛躍を試みた天才の輝き…。その輝きが突然、消えた。 (映像:ヴァンブ街5番地) ナ/1928年6月20日未明、セーヌ川左岸のヴァンブ通り5番地。佐伯祐三が病の床から突然姿を消した。(映像:佐伯祐三写真)ナ/佐伯は、その年の3月はじめから持病の肺結核が悪化。「僕は死ぬ」と、5月には、うわごとを言うようになった。 (映像:佐伯米子写真) ナ/心配した妻・米子のたっての頼みで友人たちが昼夜交代でベッドの脇に付き添った。そして、6月20日の夜明け前、看病に疲れた友人たちがうたた寝をしたわずかの隙に、衰弱して起き上がれないはずの佐伯が家を飛び出した。丸一日経った21日警察から連絡が入った。パリ郊外の街、クラマール。佐伯は以前住んでいたあたりの森をさまよった末、倒れているところを保護されたと言う。佐伯最晩年の謎「クラマール失踪事件」、その謎を解き明かす病院の資料が、70年余りの時を経て初めて明らかにされた。(タイトル)「佐伯祐三〜最期の診断書〜」 【テロップ】この番組で引用した文章中に、現在では不適切な表現がありますが、時代背景・主題の意味を正確に伝えるため使用いたします。 (映像:日本病跡学会総会) ナ/今年4月、高松で開かれた、日本病跡学会総会。病跡学(びょうせきがく)とは、歴史上の偉大な人物たちの精神構造を分析し、その「天才」に迫ろうとする学問として19世紀後半にヨーロッパで始まった。この日本病跡学会の総会で佐伯祐三研究にとって画期的な資料が発表された。精神科医の武正建一(たけまさ きんいち)さんは、佐伯の死に到る最期の2ヶ月の診断書を去年、フランス政府を通して入手した。 (映像:診断書「入院時診断書」) ナ/そこには「失踪事件」が自殺未遂であったこと、佐伯の肺結核が深刻な症状に進んでいることが明確に書かれていた。診断書、読み上げ/『ノドのあたりに首吊り自殺を試みた跡があり、両手にも噛んだ傷が数箇所ある。体の状況は芳(かんば)しくなく、熱があり、間隔を置いて呼吸困難に陥る。痩(や)せが目立ち、進行性肺結核の可能性がある。注意を要する。』(診断書)日仏医学会 会長 武正健一さん/佐伯祐三が失踪事件をおこした前後がね、いろんな精神症状がはっきりした時期なんですけども。まぁ、それも言うならば、周りの人々の表現、あの、言い伝えでいろいろかかれている事だったと思うんですけども。実際には、どういう状態でね、入院したのか、或いは、病気はいったいフランス側は何を推測していたのか。(上記解説テロップ:佐伯の周囲の人々が様々な証言を残しているが、佐伯の精神症状に関する医学的な記録は、これまで未公開だった。)ナ/佐伯の失踪を「自殺未遂」とする見方は、実は、事件直後からあった。それが否定されてきた最大の理由は、佐伯の最も身近にいた、妻、米子の証言だった。 (映像:クラマール → 佐伯祐三 & 米子写真) 米子の雑話「芸術新潮 1951年6月号」より、読み上げ/『自殺しようとして家を出たのではないと思います。ただもう一途に戸外に出たかったのでしょう。首にキズがあったというのは、息を引き取る時に首に黒いシミのようなものが浮かび出したので誤解されたのではないでしょうか?』 〈米子〉 ナ/愛するが故に自殺未遂を隠そうとしたのだろうか? (映像:フランス パリ) ナ/フランスの首都・パリ。セーヌ川左岸、パリの偉人達を祀(まつ)る パンテオン。1924年1月4日、パリに到着した佐伯とその家族は、このパンテオンに面したオテル・グランゾンムに身を寄せた。親子3人、はじめてのパリ。祐三と一人娘の彌智子(やちこ)。そして、妻の米子。それから間もなく佐伯が描いた作品。パリ遠望」。東京美術学校で学んだ印象派の大家セザンヌそのままの、色使いと構図。「アカデミズムをぶち壊せ!自分のスタイルを作れ!」野獣派の大家・ブラマンクとの出会いが佐伯を変えた。 (映像:ブラマンク自宅) ナ/友人の紹介で訪れたブラマンクの自宅。佐伯が描いたセザンヌ調のヌードは完膚(かんぷ)なきまで否定され、一陣の風と共に窓の外に飛んでいった…。 (映像:佐伯作品「黒い裸婦」) ナ/その直後に佐伯が描いた真っ黒な裸婦(らふ)の姿。急激な変化に妻の米子は戸惑いを隠せない。米子手記『佐伯祐三のこと』より「みづゑ」1957年2月号/『 女の顔はカラス天狗のように真っ黒でした。佐伯は急に人が変わったように、夢中で絵の中へ引き込まれていくように見えました。』(米子) 返信 これは メッセージ 6548 taicyk に対する返信です (映像:佐伯作品「立てる自画像」) ナ/ブラマンクから受けた衝撃の大きさを示す「立てる自画像」。その顔を佐伯は、へらで削り取った。佐伯最期の診断書を武正さんと共同研究した、東京女子医大病院の岩田誠さん。幼いころから絵画に興味のあった岩田さんは、脳神経内科と美術の世界を結びつけた研究でも知られる。東京女子医大病院 脳神経センター 所長 岩田誠さん/(「立てる自画像」について)やっぱり自分は何か、思っていた通りなんだと。これじゃダメなんだ。もっと他の自分があったはずだ、って事がこれで見つけられた。それじゃ、今までの自分は消しましょう、というような、わりあいと前向きな姿勢でやったんじゃないかと思いますけどね。決して、あれは「自虐(じぎゃく)行為」とか「自己否定」とかですね、そういう非常に深刻な形でとらえる必要はないんじゃないかと思っています。えぇ。 ナ/自分のスタイルの模索(もさく)が始まり、そして、生まれた「パリの佐伯」。パリの下町の何げない風景を真正面から見据えて次々と作品とした。 (映像:佐伯作品「レジュ・ド・ノエル」&「壁」) ナ/そのころの佐伯の代表作、「レジュ・ド・ノエル」。荒っぽいタッチで、建物の存在感は厳密に描く。卓越したデッサン力が伺える。下町の無粋(ぶすい)な壁にも美しさを見出した。石造りのリアルな質感。壁の文字も物差しを使って、真っすぐに写しとる。しかし、自分のスタイルを、つかみかけたその時…。佐伯に。結核の影が忍び寄る。 (映像:1924年9月佐伯祐三 / 宮下 → げっそり痩せた、佐伯の横顔の写真。) 武正建一さん/美校(美術学校)4年頃に、軽い喀血(かけつ)があったと。で、だいぶ(学校を)休んだってこともあるし。渡仏(とふつ=フランスに飛ぶ)する前後あたりから、何か、自分の結核…があるか、或いは、あるのではないか?どうも、自分の“先”、それほど長くない、そういった不安、或いは“死の予感”って言うんですかね。心の奥底のほうには、ずっとあったと思われるんですがね。(解説テロップ:フランスに渡る前から、結核を自覚。)ナ/結核の影に追い立てられるように、佐伯は家族と共に、1926年、いったん日本に戻る。不本意な帰国…。東京・新宿区に今も残る佐伯祐三のアトリエ。一時帰国した一家3人はここに戻った。このアトリエで妻の米子は、佐伯の死後も、40年余りをここで過ごしている。佐伯祐三研究の第一人者の美術評論家の朝日晃さん。生前の米子をこのアトリエに何度も訪ねた。美術評論家の朝日晃さん/佐伯祐三と米子との“わだかまり”みたいなものを、僕、感じちゃうんですけどね。何か…。ナ/日本の風景に絵筆が進まない、佐伯。再びパリに行こうとする熱い思いが、米子との間に亀裂(きれつ)を生む…。米子手記『強い性格』より「美術」1937年1月号/『どんなに愛する者のためにも、自分の意思を曲げたりしない。実に強い性格でございました。』(米子)ナ/米子に知らせないまま、パリ行きのシベリア鉄道のチケットを3枚、佐伯は買った…。 (映像:パリ郊外 エブラ−ル精神病院) ナ/パリ郊外の精神科専門の、エブラ−ル精神病院。1928年6月23日、佐伯が失踪から保護されて2日後、佐伯をここに入院させることを、米子は同意している。(映像:1928年6月23日付け「入院同意書」)ナ/米子のサイン(Yone’Saeki)が記された「入院同意書」。エブラ−ル病院の文書保管室。130年間、10万人の患者全ての記録が保管されている。佐伯、最期の診断書の原本もここに残されていた。エブラ−ル病院レオンさん/診断書は公開期間というものが定められていて、患者が生まれて150年たたないと、公開してはいけないことになっています。ただし、文化省や厚生省の許可で特に公開が認められる場合もあります。今回の佐伯のケースもその1つです。米子手記『悲しみのパリ』より「婦人の友」1955年9月号/『 私が祐三を見舞いに参りますと、木々の美しい、芝生の広い庭…。気の狂った夫を訪ねていく私には、その美しさがどんなに虚しいものに感じられたことでしょう。』(米子) (映像:佐伯祐三作品「カフェレストラン」) 米子手記『佐伯祐三のこと』より「みづゑ」1957年2月号/『佐伯が描いたこの絵を見たホテルの主人は、その色彩と荒いタッチに驚き、<あの人は狂人ではなかろうか。>と言っていました。』(米子)東京女子医大病院 岩田誠さん/基本的に、その作家がですね、作品を、自分の作品として残すと、そう言った時には、それを“見てくれる人”というのうを意識するわけで。その、“見てくれる人”って言うのは不特定多数であってもですね、他の他人とコミュニケーションを持ちたいと言う気持ちが残っているわけですよね。そのために、絵画として表現するわけですから。あの…、他人とコミュニケーションするって言う、その意思が残っている限り、私はやっぱり、「狂っている」とは言えないと思ってるんですよね。 (映像:佐伯作品 戦災で焼失した「米子像」) ナ/米子が語る佐伯の思い出は、新発見の診断書や、現在の医師達の所見と大きく食い違う。<C.M.> 返信 これは メッセージ 6550 taicyk に対する返信です (映像:パリ天文台 → 佐伯の作品、数種) ナ/「オプセルヴァトワール」と呼ばれるパリの天文台を見通すこの景色は、佐伯が描いた絵とピタリ一致する。カメラのレンズのように正確な佐伯の眼と冴えた技。1927年8月末、米子、彌智子と共にパリに戻った佐伯は創作活動を爆発させた。うらぶれた下町のパリに、広告の文字が躍り出す(作品「広告(アン・ジュノ)」。結核による死の予感が急がせたのであろうか。その年の末までの4ヶ月間で描いた絵の数は100枚を超えた…。(映像:佐伯祐三の作品、数種)日仏医学会 会長 武正建一さん/彼自身の人生は非常に限られていたんだけれども、その中で必死になって画びょうの完成を夢見…。ま、それだからこそ、またあの絵ができたと。ナ/最後の診断書が書かれる時間が、あと半年あまりしか残されていない。 (映像:モラン村への写生旅行 1928年2月) ナ/パリの市街地から東へ35キロ離れた郊外の村モラン。この美しい村を佐伯祐三が訪れたのは、1928年2月のことだった。現在も小高い丘の上から見えるその風景は、佐伯を惹きつけた美しさのままだ。当時、佐伯を師と仰いでいた4人の若者と、娘の彌智子(やちこ)と、妻の米子。その時のスナップ写真が今も残る。子どもの頃から足が不自由な米子(宮下→1本の杖を付いて歩く。)その米子のほうを、佐伯は振り返ることもなく前へ進む…。このモランで、佐伯は、まるで修行僧のようにひたすら描いた。村のあらゆる建物を、手当たり次第に…。モランに同行した山口長男の手記より/『 佐伯さんは毎朝7時ごろに起きて、午前、午後、少なくとも2以上を描いていました。暗くなるのも構わず必死に描いていました。』(山口長男) ナ/佐伯のデッサン力はますます冴えていく。納屋だったこの建物は、現在では一部が無くなったものの、佐伯の絵のままに70年後の今も立つ。薄い絵の具を塗り重ねたタッチ、水墨画のような油絵。しかし、その新境地も佐伯を満足させなかった。山口長男手記より/『その時は、4枚も描いたにも関わらず、結局駄目だと内心苛立っているようでした…。』(山口長男)ナ/モランの街角にキャンバスを立てて必死に絵を描く佐伯。その横に最愛の娘の彌智子がたたずむ。間も無く、2人を襲う悲劇…。佐伯が描いていたの村の中心にある教会。モランで最も目立つこの建物を佐伯は様々な角度から捉えた。(映像:「モランの寺」シリーズとモラン実景)ナ/果てしのない芸術への欲求。この時、佐伯には絵が人生の全てであった。米子手記『佐伯祐三のこと』より「みづゑ」1967年2月号/『このころから佐伯は、ふとしたことで怒るようになり、私はひどく怖く思ったことを思い出します。』(米子)ナ/芸術の高みを極める道のりで、何かが失われていく...佐伯は前へ向かって歩き続ける。米子はその後を追うのを、諦めた... |
||
New
2006/08/15
佐 伯 祐 三 編
| し け ん ど く は く |
|
し け ん ど く は く |
2006/07/14