 |
CEZANNE PAGE TOP BACK NEXT |
||||
 |
CEZANNE PAGE TOP BACK NEXT |
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 歴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1839年 | 誕生(南仏プロヴァンス地方 エクス Aix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1852年 | ゾラとの友情の始まり(1886年まで続く)。バイユと3人でエクスの田舎を遊ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1857年 | エクスの素描学校でジベールに教わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1859年 | 法律を学びながら市立美術学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862年 | ゾラの誘いでパリに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866年 | この年からサロンに出品するが、落選が続く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1869年 | 絵のモデルをしていた19歳のオルスタンス・フィケと同棲(父親には内緒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1872年 | 息子ポールの誕生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1885年 | ある女性にラブレターを送る。ゾラに僕を許して欲しいとの手紙を送る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1886年 | 47歳の頃、ゾラが「制作」を発表、この内容に深く傷ついた?セザンヌはゾラと 絶交? また父に許され同棲していたオルタンス・フィケと結婚、父死亡、金銭に 不自由しなくなった年でもあります。このため食事の量が増えたのでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1888年 | 1898年つまり10年前ににゾラは21歳のジャンヌと初めて結ばれたと言う手 紙を残している。しかしゾラとセザンヌの手紙の数、内容から1884年ジャンヌ 17歳の時にゾラと関係があったことが推測可能である。17歳の女性と関係を持 つことはゾラとしても隠したかった可能性があると考えられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1890年 | 最初の糖尿病の兆候がでたとあります。セザンヌはパリとエクスを行き来します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899年 | エクスにもどる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902年 | エクス近郊の新しいアトリエに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906年 | 67歳でなくなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時代背景 1) 時 代 背 景 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在性(自分の時代の風俗を自分の見方によって表現する)という概念が現れます。「悪の華」を書いたボードレール、レアリズム展を開いたクールベ、自分の見方により表現しようとしたドーミエに見られます。マネもその1人でボードレールやゾラから支持されています。印象派の人たちが活躍した時代はナポレオン3世がオスマン知事にパリ大改造計画をさせた時代です。オリンピックや万国博よりすごい時代、革命は起きるし、本来なら絵なんか描いていられない時代であったでしょう。パリでフランス革命が進行中の時、田舎町エクスは静かなもの。東大紛争の頃、東京では侃侃諤諤の議論をしていましたが田舎の実家に帰ると「なんてバカなことをやっているのか」などといわれ地域差、年齢差に驚いたことがあります。ある本にセザンヌは絵を描くことしか興味がなかったとあります。しかしその彼もパリに来て時代の影響を受け、写実主義、外光派、印象派などの影響を受けていきます。 | 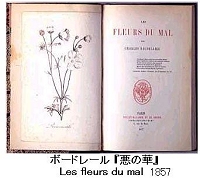 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その頃名声と富を与えるのはサロン、「サロン入選」こそが当時の画家を成功に導くただ一つの方法、しかしこのサロンの審査基準に不満を抱く人たちが多くなってきました。マネの「草食の昼食」に感激したした人たちなどが株式会社を作ってサロンに対抗し、絵を売るためにつくった集団が印象派とよばれるようになりました。サロンに入選していた人、出せば当然入っていたが出さなかったドガ,他方、入選できなかった人がこの会社をつくっています(印象派の人の多くが外光派、つまり太陽の光のもとで描くのに対し、この団体の中心人物であったドガは室内で描くことを好みました。またこの人は裕福な家庭に生まれ、法学部に席を置いたことがあります)。このとき部屋に掛けられて人が楽しめる絵をという考えが多かったようです。時代が大きく移り変わるとき生まれたこの人たちの絵は浮世絵の世界、心と通じるところがあります。だから日本人によく理解される一面もあるかと思います。 ここで、それまで印象派を眼の仇にしてきた人について述べておきましょう。ウィリアム・ブグローは、1884年フランス美術アカデミー会長になり印象派の画家達(セザンヌ、ルノワール等)を、サロン出品から落選させていた人物。印象派愛好家を基準にすれば、独善的な非情の極悪人なのであるが...『こんな絵は私にゃとても描けまへんわ!』。こういう絵を描ける人から見れば、印象派の絵はとても見るに耐えなかったと思われます。この人の絵は最近また見直され、評価割れています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ウイリアム・ブグローの作品 2点 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← 「兄弟愛」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ウィリアム・ブグロー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「蜂の巣」 1892 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 法 学 部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セザンヌは法学部に席を置いたことがあります。法科資格試験に合格したマチスにも単純化などの数学的法則が見られます。法学部は判例に基づき物事を判断する、それは保守的であるが数学的、文科系的科学、ある意味で理科系と考えられます。私は東大紛争の頃、農学部学生自治会副委員長をしていました(医師のあり方に疑問を感じ私のクラスでは私を含め、年代の差はあるもののかなりの友人が医学部に入りなおしています)。医学部から始まった紛争は全学部に広がっていきました。その運動にいち早く染まっていったのは、最年少の教養学部、次に文学部や農学部であったと思います。しかし法学部は最後まで消極的でありました。医学、工学、文学、美術などは常に新しいものを求めます。これに対してなぜ法学部は保守的なのか、なぜ過去の判例を重視するのかと不思議に思い私の弁護士さんに質問しましたことがあります。「法というものは時代を超え簡単に変わってはならない」という答えでした。確かに数学で、1+1=2、物理学で「運動の法則」などは変わってはなりません。そういう意味で科学のなかにも普遍の法則というものがあります。それはそれとして医学を例にとれば、新しい発見や新しい手術法が常に求められるのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) セザンヌ と 父 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父セザンヌの父は商売上手で銀行のオーナーにまでなってしまいます。しかし成り上がり者という眼で見られるので息子の将来を期待するようになりました。セザンヌはそんな父の気持に沿うよう努力しますが、絵を描きたいという気持ちは抑えられません。やがて父は息子が画家になりたいという望みを聞き入れます。セザンヌは父を尊敬していましたが、また恐れてもいました。父の気持ち、父の気性が痛い程わかっていたのでしょう。父としてはエクスの街で成功し、名実ともに社会的地位を築いて欲しいと思っていました。その父に報いるため、友達に頼んでサロンに入選します。セザンヌの絵から女性は男性をだめにする魔女であるという考え。しかし、その魅力から逃れられないという矛盾を感じさせるものがあります。そしてその性格は付き合いにくい堅物に見えますが、ピサロのペニスの絵、オランピア、リンゴでパリス(トロイのヘレンの物語をもじったもの)をアッといわせる、などちゃめっけなところも見受けられます。 |  セザンヌ自画像 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)モネの「日の出」が印象派の発端 ( 横山 さんのご意見 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 モネ の 「日の出」 |
モネの「日の出」をどのように見たら良いのでしょう?モネはもっと丁寧な絵を描いています。丁寧さは作家の思い入れとも関係があると思えます。タッチを活かすために、筆を置くこともありますが「日の出」の段階ははたしてそれに属する物なのでしょうか?当時、「いかに絵を下手に描くか」という雰囲気があったようにも見えてならないのです。セザンヌの絵は下手に見えますが(私には)大変丁寧です。今回見たエミールゾラの絵も丁寧な筆致でした。造形性の意味として、絵の中の世界の造形性ではなく、絵の外の造形性の丁寧さを感じます。油絵の具をまるで粘土のように扱い、その絵の具の持つ良さを十分に発揮出来るような丁寧さが見えました。これはデッサンの造形性と意味が違って来ます。ブーグローの造形性はデッサンの造形性です。油絵の具の良さを十分活かしているデッサンの仕方をしています。後期印象派の画家たちは印象派を経て、絵の具の良さをさらに拡大したように思えました。その点ではマネは非常に弱いと実物を見て感じました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
CEZANNE PAGE TOP BACK NEXT |
||||