 |
|
||||||
���{���Y���A�p���ŃZ�U���k�̊G�ƃs�J�\�̊G���n�߂Č����Ƃ��A�Ȃ��������������ł��B ���{���Y���킭�B�����Ƃ������Ƃ���͐Ԃ�V�����ɏo�鎞�A�����Ⴀ�Ƌ����ďo�Ă���B �܂�A�������V�����A���܂�ς��Ƃ����B����قǃZ�U���k�̊G�͂������������̂��B |
||||||||||||||||||||
���̃Z�U���k�̊G�ɑ��錩�� |
||||||||||||||||||||
| �Z�U���k�̊G�́A���l��m���[���̗D�����A�S�b�z�A�S�[�M�����̊���A����A�F�ʂȂǂƔ�ׂ�ƁA�킩��ɂ����A���w�ɂ��܂������F�C���Ȃ��A����ȊG�ł���B�����猩��Ƒ吅���ȂǁA���̐F�C���������̕\���B�������Ȃ���Z�U���k�Ƃ����l�͋ߑ�G��̕��Ƃ����l�A�����Ė��A�Z�U���k�̊G��͓����̉�Ƃ����ɂ��]������Ă��܂��A�����S�[�M�������A�}�`�X���ނ̊G��~������܂����B���̗��R�͂Ȃ����H�Z�U���k�̊G�͗��Ȍn�̊G�ƍl����Η������₷���ƍl���܂��B�����M�A���n�ɐi�ނ����n�ɐi�ނ����������Ƃ�����܂��B���n�̕��������̐l�ɐe���݂₷���Ɗ����܂��B�����≻�w�A���w��菬������j�̕����e���݂₷���B�Z�U���k�̖����u���R���~���`�Ƌ��`�Ɖ~���`�ɂ���Ĉ����Ȃ����B���R�͕��ʂ����[���ɂ����đ��݂��܂��B���̂��߁A�ԂƉ��Ŏ��������̐k���̒��ɋ�C������������n��������K�v��������̂ł��B�v���̌��t���玄�̓Z�U���k�̊G�͗��Ȍn�̊G�ł͂Ǝv���܂����B�Z�U���k�̊G�ɂ͍��������F�߂��܂��B���ÁA�ʓx�F�ʂ̈Ⴂ�ɂ��O��̊W���l����Ƃ��A��O�̂��̂𖾂邭�A�܂��͐F�ʑN�₩�ɕ`�����Ƃ͑Ώۂ�����炵�������鍇����������A�Z�U���k�͌��������̍��������d���Ǝv���܂��B�Z�U���k�͕��̂����L�����p�X�̏�ʼn�ʍ\��������V�������@�����݂��ŏ��̐l���ƌ����ėǂ��ł��傤�B�Z�U���k�̗L���ȑ��̌��t�Ɂu���R�ɑ����ăv�b�T������蒼���v�Ƃ������t������܂��B����̓v�b�T���̉�@�݂̂��Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���R��`���d�Ȃ�������w�ƊG�悪�Z����ڎw���Ă����B������]���̏����ɏo�Ă���^�C�g���Ɠ����^�C�g���̊G���݂邱�Ƃ��o���܂��B�s�T���Ȃǂɉe�����Ȃ���Z�U���k�͔ނȂ�̐�̒T���𑱂����B | ||||||||||||||||||||
| �ӔN�͒��ۂɌ��������ƌ����Ă܂��B�Ⴂ���̍�i������ƌ`���͂����肵�Ă��܂����ӔN�ɂȂ�ƌ`���͂����肹���^�b�`�ƐF�ʂŃT���g�E���B�N�g���[����`���Ă���l�Ɍ����܂��B���ꂪ�Z�U���k�̒��ۉ��ƌ�����R���Ǝv���܂��B�u�f�b�T���ƐF�ʂ͂��͂��ʂł��܂���B�F��h��ɂ�ăf�b�T�����ł�������܂��B�v�Ƃ����Z�U���k�B���͔ނ����A�a�ɂ��A������܂��͖Ԗ��ǂɂ���āA���Ȃ莋�͂������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�܂�Ɏq��ʂ��Č����i�F�͌`�͂͂����肹���A�F�ʂ͂܂���Ȕ����܂݁A�F�ʂ͌����荇���A��͐����łȂ��A��������悤�ɂȂ�Ǝv���܂��B����Ȋ�Ŕނ̔ӔN�̃T���g�E���B�N�g���[�������Ă��܂��B�s�J�\�̔ӔN�̊G������ȂƂ��낪�����܂��B���l�A�h�K�̍�i�����������ӂ��Ɍ��܂��ƁA�͂����胂�m�������Ȃ���Ԃŕ`���ꂽ�G�́A���ʂł͌����Ȃ����̂�������G�ƂȂ�Ǝv���܂��B |  ���[������݂��T���g�E���B�N�g�[���R 1905 |
|||||||||||||||||||
���̗F�l��Asyuranote����̃Z�U���k�� |
||||||||||||||||||||
| �Z�U���k���u����G��̕��v�ƌĂꂽ�̂́A�[�I�ɂ����ΊG����\������G�������g����u�F�ʁA�`�v���̂��̂̌ŗL�̐����������������Ȃ̂ł��B�܂肻���ɁA�u������\�����邽�߂̎�i�Ƃ��Ă̈Ӌ`�v�ł͂Ȃ����`�ړI���̂��̂Ƃ��Ă̈Ӌ`���݂��Ƃ������Ƃł��B���̍l�����͂��̌�̗��̔h�A�����h�����o�Ă��璊�ۊG��A������p�ɂ܂Ŗ��X�Ǝp����܂����B���̂��Ƃ̂�����̈Ӌ`�͌|�p�Ɂu���Ր��v��^�����Ƃ������Ƃł��B�F�A�`�Ƃ����u���`�G�������c�v�͉��y�ɉ����鉹���Ɠ������C���^�[�i�V���i���Ȃ��̂ł��B�܂肻���͖������ʂɗ������꓾����̂Ƃ������Ƃł��B | ||||||||||||||||||||
�G�~�[���E�x���i�[���ƃZ�U���k |
||||||||||||||||||||
| ���̐l�̓S�b�z��S�[�M�����Ƃ����ʂ��Ă��܂��B���������̕�����Ƃ��čō��̐l�A�Ȃ����̐l�͂��������������ƕ��ʂł����̂ł��傤�B���ł���Όg�тŖ����b�������܂��������͎莆�����ł��B�M�܂߂ŁA�Ȃ�قǂ����Ȃ�ł����A�[�����܂����Ƒ���ɂ�����ł��b�����邱�Ƃɂ����Ă����̂ł��傤�B�J�[�l�M�[�́u�l�����v�Ƃ����{������܂����A�G�~�[���E�x���i�[���͐l�Ɍ�点��V�˂ł������Ǝv���܂��B |
 �G�~�[���E�x���i�[�����摜 |
|||||||||||||||||||
���̗F�l�ŃA���U�X�ɏZ�� ���R ����̂��b �@ |
||||||||||||||||||||
�Z�U���k�͔����܂߂ĂP�X�F�̃`���[�u����G�̋���g�p���Ă��܂������A���̃`���[�u����G�̋�͎g���Ă��Ȃ������悤�ł��B�{���[���̕���Z�U���k�̓e�����L�L�̖т̕M���v�킹����炩���M�����p���Ă����悤�ł��B�܂��A�F���g���x�Ƀe���s�����ŕM���Ă����悤�ł��B�W���[�i���X�g�̃W�F���E������̏ё�����˗��������̕���l�̊�̏ڍׂ͈�ԍŌ�ɕ`�����悤�ł��B�����̋L�q���炩�Ȃ�u�F�̑���v���C�ɂ��Ă����̂ł͖������ȂƎv���܂��B�܂��A�G�̋�����������ɒZ���Ԃŕ`�����Ƃ��Ă����悤�ɂ��v���܂��B���G�̋���g����ŁA���̕��@�́u�`���ɂ����v�悤�ȕ��@�Ɏv���܂��B���G�̋�̐����ɉ����̂ł͂Ȃ��A�������邩�̂悤�ȕ`�����ɂ��v���܂���A��۔h�̊G�͂ƂĂ�����ɑς��Ȃ������Ǝv���܂��B���̐l�̊G�͍ŋ߂܂���������]������Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||
���̗F�l�ŃA���U�X�ɏZ�� ���R ����̂��b �A |
||||||||||||||||||||
| �Z�U���k�̈Ӑ}�������������t�ōL�߂��̂̓G�~�[���E�x���i�[���ł��B��۔h�̊G��̓_�_�C�Y���Ɠ��l�ɔ��̐��I�v�f�݂̂Ő��藧���Ă��邱�Ƃ��������Ă����悤�ɂ����v���܂��B���Ƃ��Ă̈�۔h�ł���u�����۔h�v�ɂ͌������Ȃ��l���̂悤�Ɏv����̂ł��B�G�~�[���E�]���̓W���[�i���X�g�Ƃ��āA��۔h�̓`�d�ɑ����ɍv�������Ǝv���܂��B����ǁA���̈�۔h�̎v�z�ɃZ�U���k�͏������C�������Ă����悤�ɂ������܂��B�R���[�̗�����s�T�������݁A�Z�U���k���p������ł����A�u�����Ȃ�����`���v�Ƃ�����۔h�ɂƂ��Ċ̐S�̕����́u���̐��v�̐����ɑł�������Ă����悤�ȋC�����܂��B�Z�U���k�͊G��Ƃ��Ă̔������̒T���̂��߂ɓc�ɂֈ������������悤�Ɏv���܂��B | ||||||||||||||||||||
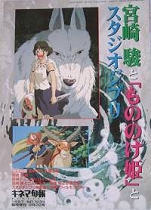 |
��������肳������āA�p���Ō|�p�̉p�C���R�z���Ă����G��`�����Ƃ�������ōs���܂������A�v�����قNJG�ɂȂ镗�i�ɏo��܂���ł����B�u���������|�p�v�Ƃ���Ȃ�A�������镨�͂悤�悤�Ȑl�X�̎v�f�̒f�Ђł����B�g�C���������p���A�J�t�F�̖����B�n���S�ɏ��l�X�B�X�N�[�^�[�ɏ��l�X�B�W������B�����|�p�w�Z�B���A�[���̉f��̎��ʉ�B���̃p���̍Ő�[�̌|�p�́u���{�̃A�j���v�ł��B�X�^�W�I�W�u���̍�i�ł��B�����|�p�w�Z�̓W������ōÂ���Ă���̂��{��x�W�ł����B���A�[���Ő�s���ʉ�ɍs����Ȃ��Ă����̂́u�C�m�Z���X�v�Ƃ�����i�ł��B���i���U�̑O�ō��R�̐l������͒����l�ł��B | |||||||||||||||||||
| ���̉�L�̓W����ɂ͒N��l���q����͓����Ă��Ȃ��ō�Ƃ��ۂ�ƍ����Ă��邾���B�����Q�������W������́u�V�e�f�U�[���v�Ƃ����p���ł��R������ꏊ�Ȃ̂ł����A����̎�Òc�̂�NAC�͓��{�l�̌|�p�Ƃ̏W�܂�B�u�V�e�f�U�[���̏o�i�҂̎��̒ቺ�̂��߂ɁANAC�ł�������ꂽ�̂ł́H�v�Ƃ����\�������ɂ��܂����B�I���I������̉�L�Ƀr�f�I���u���[��������Ƃ��������͍Ő�[�̌|�p��ǂ�����������Ƃ��ĊԈ���Ă��Ȃ������m�F�o���܂����B | ||||||||||||||||||||
 |
|
||||||