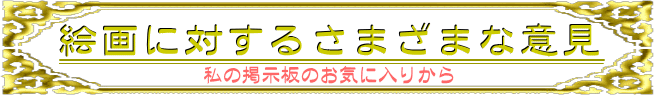
「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/08/01
← 戻る (「 女性美の500年 」展 へ) || ( 心の傷と作品性 へ) 進む →
|
白矢 ...この前見ました「美の巨人たち」で、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」によく似た絵、17世紀初頭に描かれたグイド・レーニ作『ベアトリーチェ・チェンチの肖像』に心惹かれましたので、チョット書いてみたいと思います。ベアトリーチェ・チェンチは悲劇の少女、これから死刑になる、その死を前にして振り向いた顔の悲しさ、あきらめ、はかなく短い命を感じさせる。「真珠の耳飾りの少女」をフェルメールはこれを意識して描いたらしいとの解説。人は振り向くとき、どんな顔をするのであろうか、「...人は誰もただ1人ふりかええる、ふりかえっても風が吹いているだけ...」という歌がありましたが、当人にとっては振り返ることは未練や懐かしさ、過去への踏ん切り、それを自分では気付かないまま振り返っているのでしょう。振り返る女性を描きとめる画家は一心不乱に筆を傾け、一瞬の思いを描きとめる。一度自分なりの振り返る女性を描いてみたいものです。ターバンを二人ともしていましたが、人形を描いていて発見したことは帽子の役割です。帽子は空間の動きをつくり、またその大きさを変えられること、動きをつくられることなど、絵作りに一役買うということです。「振り返る帽子の女」、私なりのものを描いてみたくなりました。
フェルメールの絵からは現実の女性の存在感は感じても、そういった物語は見えて来ないし、必要ともされていません。レーニは同じチェンチ像を何枚か描いているようですし、テレビでも言っていたように版画の流通でその画像をフェルメールが見ていたというのは頷けますが、おそらくフェルメールに関心があったのは純粋に図像的なもので、悲劇の王女様のお話ではなかったろうと思います。なればこそ女性のターバンだとか青色の使用といったチグハグな考証となるのでしょう。晩年のフェルメールは演出過剰なポーズや薄べったい感情表現に向かい、質が落ちているように思います。どうも見る側というのはこうした安易な意味付けを欲するもののようで、「美の巨人」で有名でもない「ベアトリーチェ・チェンチの肖像」が肖像画のベスト3に選ばれたのも、このサイドストーリーに負うところが大でしょう。でも、そうした表面的な意味性はすぐに消費されてしまいます。チェンチ像が忘れられた作品であったことは当然といえば当然の事で、ヨーロッパの美術館にはそういったテーマの作品がゴマンとあります。物語を知って見に行けば汲めども尽きぬロマンの宝庫で、ベアトリーチェ・チェンチの話がそれらの中に埋没してしまったのは致し方ないところでしょう。モダニズム絵画はそうした文学性の優位性を排除しようとしてきました。絵画は絵画であって説明画(イラストレーション)ではないということで。しかし、今また物語性の復活が取りざたされています。物語に普遍性があればイラストでもいいじゃん、ということなのでしょう。しかし、物語に普遍性というのはありえません。なぜなら物語がそもそも普遍的な事象を説明するための道具だからです。絵画はまたその下位に甘んじようとしているのです。おそらく一般受けはしやすいでしょうが、僕はどうもいただけません。その意味では僕も北方系の絵描きなのかもしれません。 |
← 戻る (「 女性美の500年 」展 へ) || ( 心の傷と作品性 へ) 進む →
「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/08/03
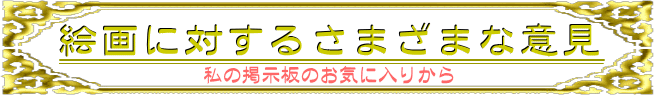
医院について M A P Art Work 医学と芸術の旅 学寮 向ヶ岡

